|
http://www.joho-kyoto.or.jp/~acdfo/top.html
���j�s�s�u���s�Ɩk���v�ɂ�����
���ۊό��̌���Ɖۑ�
�\�k���A�W�A�n��ɂ����鍑�ۊό��𗬁E�A�g����������Q�s�s�\
�P�D�͂��߂�
�ŋ߁A�k���A�W�A���Ɉʒu���鍑�X�i���{�A�����A�؍��A�����S���A���V�A�A�k���N�j�ɂ����鍑�ۊԂ̐l�I�𗬂������ɂȂ��Ă���B�������Ȃ���A���̒������e���Ԃŋύt����ꂽ�ł��邩�ƌ����Ό����Ă����ł͂Ȃ��B�����A���A���Ȃǂ̓���̂Q���Ԃ̐l�I�𗬂���̂ƂȂ�A�����̍��X�ȊO�̗���Ƃ̊i������ł���B�܂��A�����ȓ��������������R���ɂ�����ό������́A�����ؒn�挗�A�g�v�����[�V�����̌��ʂł��邩�ƌ����A�����ł��Ȃ��B�Ǝ��̍��X�̐U�������̐��ʂ��قƂ�ǂł���B����A�����̂R�����܂߂āA���Y�n�悪����ɐl�I�𗬂�ڎw���Ȃ�A����ɋٖ��ȋ��́E�A�g���K�v�ł���A�ό��J���E�U����i�߂��@�������Ƃ��L���ł��낤�B���̂܂܂̏�ԂŐi�߂A���݂̕s�ύt��Ԃ��p�������Ċg�傷�邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
�Ƃ���ŁA�ߔN�A�k���A�W�A���̍��ۊό��������ɂƂ̊|�������e��t�H�[�����ȂǂŔ��\�����悤�ɂȂ��Ă������A��̓I�ȃA�N�V�����E�v���O�����ƂȂ�Ɛ�ɐi�߂Ȃ��Ȃ��Ă���B����A�k���A�W�A�̊ό��𗬊g��ɂ́A�V�X�e���I�ȑ����Ԋό����́E��g���s���ł���B�g�߂ȎQ�l����Ƃ����A�A�Z�A��10�J���œW�J����Ă���ό��𗬊g��L�����y�[���i�A�Z�A���E�p���_�C�X�ό��헪Asia�fs�@Perfect
10�@Paradise�j������B�A�Z�A���n��̍��ۊό��̓����́A�k���A�W�A�̓����ȏ�Ɋ����ȗl���������Ă���B�n����̋��łȊό��U���ɂ́A�܂��n��S�̘̂A�g����я�M���d�v�ł���Ƃ̔F���ŁA����O�ɑ�X�I�ȓ����������Ă���B�܂��A�e��̖��͓I�Ȋό����T�i�n����R���r�l�[�V�������ʍq��^���Ȃǁj��n��������ȊO�Ɠ����Ɉ�O�̃c�[���X�g�ɂƂ��Ė��͂Ɋ���������̂\���Ă���B�����A����̊ό��v���t�F�b�V���i���l�ޗ{���ɗ͂����A�A�Z�A�������Œ���I�E�����I�ȋ���̐���~���Ă���B
���āA�k���A�W�A���ł̊ό��U������Ɋւ��āA�������ɂ͒P�Ƃ̍��E�n�悾���łȂ��A�n��S�̂̋��́E�A�g�̕K�v���������Ƃ��K�v�Ƃ���Ă��邪�A�����̒i�K�ł́A���[�_�[�I�Œ��j�I�ȑ��݂̌��o���K�v�ł���A����炪�傫���O�i�����錴���͂ɂȂ�B���̊ϓ_����A��N�A���s�E�k���Ԃł̊ό��𗬃t�H�[�����̎��݂����������A����ɋ��́E�A�g�̐������i����邱�Ƃɂ��ό��𗬊g��̉\�����A���s�s�݂̂Ȃ炸�A�k���A�W�A�n��S�̂ɐ�����ł��낤�ƍl����Ɏ������B���s�s�̊ό��s�s�Ƃ��Ă̌��́A�܂����ݕ�������_�̉𖾁A����Ȃ�ό��U���̕��������������邱�Ƃɂ��A��芈���Ȋό��U�����ڎw����̂ł͂Ȃ����Ƃ̍l������A�{�e�[�}��_���邱�Ƃɂ���B
�Q�D���j�s�s�u���s�Ɩk���v�ɂ����鍑�ۊό�
�Q�|�P�D���s�ɂ�����ό��̌����Ɖۑ�
�u���{�̊ό�������������j�s�s�E���s�v�@�@�������s1200�N�̗��j�������s�́A���̊��ԁA�����E�o�ρE�����E�Z�p�Ȃǂ����镪��ŁA���{����ѓ��{�����̒��S�I�����������Ă����B��s�s���@�\�Ɨ��j�s�s�E���s�̌ŗL�̒����i�ς⎩�R���j�I���y�������Ă��邱�Ƃ��A���ۊό��s�s�E���s�̍ő�̓����ł���B�����̎��R���j�I��Y�𒆐S�Ƃ��鋞�s�ό��̖��͂ŁA�����E�C�O���疈�N�A4,000���l�̊ό��q���K�₷����{�̑�\�I�Ȋό��s�s���`�����Ă���B2003�N�̋��s�s�̊ό��q���i���{�l����ъO���l�j�́A4,374���l�ł���A�O�N��3.7���̑����������Ă���B�������A������[�I�Ɍ����A���s�͊ό��I���𑽂͂��L���Ȃ�����A�}�\�P�Ɍf������Ă���ߋ�6�N�Ԃ���т���20�N�Ԃ����Ă��傫�ȐL�т͌���ꂸ�A������g�����h��悵�Ă���B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�\�P�@�@���s�ό��q���i���{�l�y�ъO���l�j�̐���
|
|
1998�N |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
����(��l)
�O�N�䁓 |
38,973 |
38,991 |
40,512 |
41,322 |
42,174 |
43,740 |
|
(0.1) |
(0.1) |
�i3.9�j |
(2.0) |
(2.1) |
(3.7) |
|
���A��(�g) |
29,877 |
29,868 |
31,089 |
31,405 |
32,059 |
32,959 |
|
�h��(�g) |
9,096 |
9,123 |
9,423 |
9,917 |
10,115 |
10,781 |
|
�O���l�q(�l)
�O�N�䁓 |
400,017 |
394,588 |
398,252 |
383,897 |
480,828 |
450,433 |
|
(-
3.3) |
(-1.4) |
(0.9) |
(-3.6) |
(25.2) |
(-6.3) |
�o���j���s�s�Y�Ɗό��ǁዞ�s�s�ό������N���
����A�K���O���l�̓�������Ă݂�A���{�ɂ�����L���̊O���l�K��s�s�ł��邱�Ƃ������Ă���B���{�ւ̖K��O���l�S�̂Ƌ��s�ւ̖K��҂��r����ƁA�S�̂�10���O��̃V�F�A�Ő��ڂ��Ă���B���ЕʂɌ���A�����J�l����ɏ�ʂ��߂Ă���A���Ă̊��������s�s�Ƃ̔�r�ő傫�����Ƃ��킩��i�}�\�Q�j�B���̑��A���N�̃x�X�g10�J���ɂ́A�C�M���X�A�I�[�X�g�����A�A�h�C�c�A�t�����X�A�J�i�_�Ȃǂ������L���O�ɓ����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�}�\�Q�@�@�O���l�q���Еʃx�X�g�T�i���s�ɂ�����h���x�[�X�j�@�@
|
2000�N |
2001 |
2002 |
2003 |
�@ |
|
���E�n�� |
�h���Ґ��l�E������ |
���E�n�� |
�h���Ґ�
�l�E������ |
���E�n�� |
�h���Ґ��l�E������ |
���E�n�� |
�h���Ґ��l�E������ |
�@ |
|
�@��p |
105,935
(26.6) |
�@�A�����J |
115,937
(30.2) |
�@�A�����J |
130,785
(27.2) |
�@�A�����J |
128,373
(28.5) |
�@ |
|
�A�A�����J |
102,351
(25.7) |
�A��p |
94,055
(24.5) |
�A��p |
71,163
(14,8) |
�A�؍� |
54,502
(12.1) |
�@ |
|
�B�؍� |
29,471
(7.4) |
�B�؍� |
30,328
(7.9) |
�B�؍� |
51,929
(10.8) |
�B��p |
50,448
(11.2) |
�@ |
|
�C���` |
28,674
(7.2) |
�C���� |
23,418
(6.1) |
�C���� |
29,331
(6.1) |
�C���� |
28,377
(6.3) |
�@ |
|
�D���� |
20,311
(5.1) |
�D���` |
21882
(5.7) |
�D�C�M���X |
20,446
(5.5) |
�D�C�M���X |
24,774
(5.5) |
�@ |
|
�@ |
�����j���s�s�Y�Ɗό��ǁu���s�s�ό������N��v
�ߔN�A���{�S�̂ɃA�W�A����̊ό��q�̃V�F�A���傫���Ȃ���邪�A���s�ł͂��̌��ۂɘA���I�ȓ����͌����Ă��Ȃ��B���̌X���́A�}�\�R�̖�20�N�Ԃ́A�K���O���l�̖K��n�ʖK�◦�̉��~��������c���ł���ł��낤�B���ł������l�̐L�ї��Ɋւ��āA�L���x�͓��{�S�̂̂���ɔ䂵�āA�����đ傫���͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���ۊό��s�s�E���s�Ƃ��āA�����ɍ���A�K���O���l�A�Ȃ����A�A�W�A�l��U�v�ł��邩���A�S�̐���L�����Ƃɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ낤�B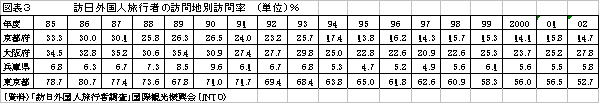 (��) �K�◦�Ƃ́A�u����̗��s���ɓ��Y�n��K�₵���v�Ɠ������Ґ����S�Ґ��~100�ɂ�苁�߂����́B
(��) �K�◦�Ƃ́A�u����̗��s���ɓ��Y�n��K�₵���v�Ɠ������Ґ����S�Ґ��~100�ɂ�苁�߂����́B
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@21���I�̋��s�̔��W����ъ������ɁA�ό��E�ό��Y�Ƃ������A�]���̊�Y�ƂƂ����Ă����@�ێY�Ƃ̕s�U�Ȃǂ��ό��Ŕ҉���Ƃ̊��҂̐��͑傫���B���̂悤�Ȏ����ɁA���s�s��2001�N�ɁA2010�N�ɔN��5,000���l�̊ό��q�i���{�l����ъO���l�j���K���䂪�����\����u5,000���l�ό��s�s�v����������v���������肵�A���݁A�i��ł���B
�Q�|�Q�D�k���ɂ�����ό��̌����Ɖۑ�
1978�N�ɒ������{�͉��v�E�J�������ł��o���Ĉȗ��A���ƌo�ϔ��W�𐄐i���鎑�����B�̎�i�Ƃ��āA�ό��U����}��A���ې����z�e����V���b�s���O�Z���^�[�̌��݁A��ʖԂ̊g�吮���A�ό��{�݂ɂ�����T�[�r�X��^�c�ȂǁA��I�Ȋό��J���ɓw�߂Ă����B
���ۊό��@�ցiWTO�j�́A2020�N�ɂ����鐢�E�ό��̒����I�W�]�̒��ŁA�����̖��i���鍑�ۊό��Ɍ��y���Ă���B�u�����́A1��3,710���l�̊O���ό��q���}����w������m�n�D�P�̍��x�ɂȂ�A�����A���E�Ɍ����Ă͒����l���s�҂P���l���o���w���o���m�n�D�S�̍��x�ɂȂ邾�낤�v�Ƃ̗\���ł���B���̗\���̔��\�̌�ɁA2001�N�̃A�����J���������e�������Ő��E�I�ɍ��ۊό��q�̗������݂����������A�����͂�����������A�����2003�N��SARS�i�V�^�x���j�Ɍ�������@�ɗ������ꂽ���̂́A�}���ȕ������قڐ��������Ă���B�����āA�߂�������2008�N�̖k���I�����s�b�N�����2010�N�̏�C�̖���������ʂ̍��ۊό��ʑ����̖ڕW�ƒ�ߐi��ł���B�����A2001�N�̐��E�f�Ջ@�ցiWTO�j�������@�ɁA�����ό�����芪���z�e���A���s��ЁA�q���ЂȂǂ̊ό��Y�Ƃ��̂��̂��傫�Ȕ��W�𐋂�����A�����̍��ۊό��́A���܉���I�Ȏ����ɂ����������Ă���Ƃ�����B���̂悤�ɖ������钆���ɂ����Ē��j�I�Ȗ����������Ă����̂����j�s�s�E�k���ł���B�����̗��j��̈�Y�ł���A�V����L��A�̋{�����@�A�i�R�����A�V�d�����A��������A���\�O�ˁA��a���A�~�����Ȃnj����͑����A���E�e������̊ό��q�𖣗����A2008�N�̖k���I�����s�b�N�܂Ōp�����čs�������ȌX���ɂ���B
�@�@�@�@�@�}�\�S�@�k������я�C�ɂ�����O���l�K��Ґ�
|
���ځ@�N�@�@�@�@�@ |
���E���k�� |
�O�N�� |
���{���k�� |
�O�N�� |
���E����C |
�O�N�� |
���{����C |
�O�N�� |
|
1995�N |
1,665,246 |
�| |
424,308 |
�| |
1,075,439 |
�| |
485,098 |
- |
|
1996 |
1,761,608 |
105.8 |
429,506 |
101.2 |
1,154,841 |
107.4 |
562,672 |
116.0 |
|
1997 |
1,868,570 |
106.1 |
430,439 |
100.2 |
1,299,923 |
112.6 |
599,690 |
106.6 |
|
1998 |
1,781,800 |
95.4 |
435,156 |
101.1 |
1,175,520 |
90.4 |
508,921 |
84.9 |
|
1999 |
2,050,159 |
115.1 |
456,451 |
104.9 |
1,287,280 |
109.5 |
498,935 |
98.0 |
|
2000 |
2,379,637 |
116.1 |
543,319 |
119.0 |
1,438,992 |
111.8 |
537,565 |
107.7 |
|
2001 |
2,398,790 |
100.8 |
506,662 |
93.3 |
1,516,478 |
105.4 |
561,094 |
104.4 |
|
2002 |
2,664,535 |
111.1 |
564,546 |
111.4 |
2,159,417 |
142.4 |
822,625 |
146.6 |
|
2003 |
1,851,000 |
69.5 |
292,256 |
51.8 |
1,989,968 |
92.2 |
722,604 |
87.8 |
|
2004 |
2,681,000 |
144.8 |
523,059 |
179.0 |
- |
- |
- |
- |
�Q�l�j�u��C�������v�v(��C�s�������ƊǗ��ψ����)
�@�u�k���s�ό��ǁvhttp://www.bjta.gov.cn/2j/lyzl/tjzl.jsp�@
�@�@���Ӂj2003�E2004�N�x�k�����l�i���E�S�́j�͊T���B
�������Ȃ���A�}�\�S�Ō�����悤�ɗ��j��Y�Ɋւ��ẮA�卷�̂����C���A�ߔN�A�}���ɍ��ۊό��ʂŒ������ł̃V�F�A���g�債�Ă���B�܂��A���E�S�̖̂k������я�C�ւ̈ړ����r����A�k���̃V�F�A�̊ɖ��ȉ��~��������B�����A���{�l�̖k������я�C�ւ̓����́A�ߔN�}���ɏ�C�V�t�g�����A���݂��p�����ł���i�������A2003�N��SARS�̂��߂ɗ�O�I�ȔN�x�Ɣ��f����j�B
�Q�|�R�D�u���s�Ɩk���v�ɂ����闼���j�s�s�̍��ۊό���̈ٓ�
���j�s�s�E���s����іk���Ɋւ��āA���E�̊ό��q�U�v��A�ގ�����L���闼�s�s��
��r�ɂ��Đ��l�𒆐S�ɍs�������i�}�\�T����тU�j�B�@�@
|
�}�\�T�@�@�����ɂ�����O���l���q�� |
|
�@ |
���{�S�� |
�O�N�� |
���s |
�O�N�� |
���s���S�́i���j |
�����S�� |
�O�N�� |
�k�� |
�O�N�� |
�k�����S��
(���j |
|
1999 |
4,437,863 |
�| |
394,588 |
98.6 |
8.9 |
8,432,050.0 |
�| |
2,050,159 |
115.1 |
24.3 |
|
2000 |
4,757,146 |
107.2 |
398,252 |
100.9 |
8.4 |
10,160,432.0 |
120.5 |
2,379,637 |
116.1 |
23.4 |
|
2001 |
4,771,555 |
100.3 |
383,897 |
96.4 |
8.0 |
11,226,384.0 |
110.5 |
2,398,790 |
100.8 |
21.4 |
|
2002 |
5,238,963 |
109.8 |
480,828 |
125.2 |
9.2 |
13,439,497.0 |
119.7 |
2,664,535 |
111.1 |
19.8 |
|
�����j�������Ɗό��Ǔ��v�E���{�̍��ۊό����v-2003�i����15�N�j |
���s�s�̐L�ї��ƃV�F�A�Ɋւ��ďq�ׂ�A�u���s�v�ɂ�����L�ї��͕��ϓI�ɔ����Ƃ����ׂ��ł��낤�B�����A�u�k���v�̐L�ї��Ɋւ��ẮA����10�N�ԁA2003�N��SARS�����������A�����łقڂQ���̐L�т������Ă��邱�Ƃ�����������B�Ȃ��A2001�N�x�ɂ�����L�т̓݉��́A�A�����J���������e���̉e���ƍl������B���ꂼ��̍��ɂ�����V�F�A�͂ǂ̂悤�ȓ����ɂȂ��Ă��邩�B�u���s�v�ɂ����Ă͓��{�S�̂̂W�|�X���A���Ȃ킿10���ɖ����Ȃ��ł���ʂ����č��ۊό��s�s�Ƃ����邩�����ꂻ���ł���B����ɔ����āA�u�k���v�̃V�F�A�͒����S�̂�20�|24���Ƃ��Ȃ荂�������Ő��ڂ��Ă���B�������Ȃ���A�k���ɂ�����V�F�A�͒����̑S�̂��猩��A�ߔN�A���~�������ǂ�u���s�v�Ɠ��X���������Ă���B�Ƃ���ŁA�������݂ŁA�����j�s�s���ǂ̂悤�ɖK�₵�Ă��邩�����������B�����l�ɂ�鋞�s�K�₪���|�I�ɏ��Ȃ����Ƃ��킩��B�����A���{�l�̖k���K��́A2003�N�x�������āA20�|25���̐��l�Ő��ڂ��Ă���B�S�|�T�{�̍�������Ƃ�����B
|
�}�\�U�@�@�@�������ݖK��Ґ� |
|
�@ |
���������{ |
�O�N�� |
���������s |
�O�N�� |
���s�����{
(��) |
���{������ |
�O�N�� |
���{���k�� |
�O�N�� |
�k��������
�i���j |
|
1999 |
294,937 |
�| |
15,784 |
�| |
5.4 |
1,855,197 |
�| |
456,451 |
�| |
24.6 |
|
2000 |
351,788 |
119.3 |
20,311 |
128.7 |
5.8 |
2,201,528 |
118.7 |
543,319 |
119.0 |
24.7 |
|
2001 |
391,384 |
111.3 |
23,418 |
115.3 |
6.0 |
2,385,700 |
108.4 |
506,662 |
93.3 |
21.2 |
|
2002 |
452,420 |
115.6 |
29,331 |
125.2 |
6.5 |
2,925,553 |
122.6 |
564,546 |
111.4 |
19.3 |
|
2003 |
448,782 |
99.2 |
28,377 |
96.7 |
6.3 |
2,254,800 |
77.1 |
292,256 |
51.8 |
13.0 |
|
�����j�k���s�ό���ttp://www.bjta.gov.cn/2j/lyzl/tjzl.jsp�@�@�@�@���Ӂj���������s�A���{���k���͏h���x�[�X |
�R�D���j�s�s�w���s�Ɩk���x�̊ό��w���𗬁E�A�g��̏d�v��
���ۊό��U����A��X�̓_�ŗގ�����L�������A���ʂ̖��_�������s�s�̌𗬁E�A�g���d�v�ł��邪�A�ǂ̂悤�ȑ��ʂ��l�����邩�����������B
�u�Ós�E���j�����ۑ��v�@���̊ϓ_���痼�s�s���l�������ꍇ�A��苭�����݂ł̌𗬁E
�A�g���K�v�Ƃ���Ă���B���Ƃ��A�u�k���̌ӓ��E�l���@�v�Ɓu���s�̒��Ɓv�Ɋւ��āA���҂Ƃ����ꂼ��̓s�s�̗��j�������ے�����i�ςł��邪�A�ۑ��ɂ͋��ʂ̔Y�݂�L���Ă���B���s�ł́A�ߔN�A�ی�ۑ��̈ӎ������܂�^��������ɂȂ���邪�A����̖k���̌ӓ��E�l���@�͒����̋ߑ㉻�ƂƂ��ɁA���ł���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��i���F�ӓ����l���@�Ɋւ��āB�ӓ�(�t�[�g��)�Ƃ͉���/�H�n���w���B���R�����x�̓��̗����ɍg�F��D�F�̕ǂ������A�ǂ̒��Ɏl���@�ƌĂ��`���I�ȏZ����ԁB�����̑����̎l���@�͐��������Ɍ������ꂽ�Ƃ����B������͂�łS���̉Ɖ�������̂������ł���j�B
�u���j�����ʈȊO�̖��͂̐��ݐ��v�@�@���łɌ����������Ă������A���j�������ւ闼�s�s�́A���ۊό��q��傢�ɖ��������邪�A����̏ɂ���B���������āA���j�����ȊO�̖ʁA�Ⴆ�A�ߑ�I�ȑ��ʁ\��[�Z�p�A�t�@�b�V�����Ȃǁ|�̊ϓ_����A�V���Ȋό��U�v�̖��͂�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B
�u�O���l�U�v��@�̏������v�@���ɁA���s�ɂ����Ă͂��̖ʂł̍H�v���K�v�Ƃ����Ǝv���邪�A�O���l�ό��q�̑��ʂ̊g��ƂƂ��ɁA���Čn�ȊO�̊O���l�U�v�̎�@�Ɋւ��āA�𗬁E�A�g���K�v�Ƃ���Ă���B�����ɂ��A���E�Ɍ����Ă̊ό��U�v�̐�`�g�D�A���f�[�^���M�A�l�ޗ{���E�z���Ɋւ��ẮA�k���̍H�v�ƔM�ӂ͒��ڂɒl����B
�S�D�܂Ƃ߂ɂ����ā\���j�s�s�u���s�Ɩk���v�𒆊j�Ƃ��鋤���ό��U���Ɩk���A�W�A���\
�����j�s�s������і��_��F���������A���݂Ɍ𗬁E�A�g�����߁A��_��⋭���邱�Ƃ��\�ł���A�k���A�W�A���Ń��[�_�[�I���͂����A���Y�n��̊ό��������̋��_�Ƃ��Ȃ�A�����ɂ��̒n�挗�S�̂������ł��邱�ƁA�^���Ȃ��B�u���s�E�k���v�ό����i�v�����[�V��������j�s�s�Ƃ��Ă̊ϓ_����A�܂��ό������̐V���Ȕ��@���s�����Ƃ��d�v�ł���B����ɁA�قȂ������_����̖��͂��J�����Ă����K�v�����낤�B
���Y�n��̑傫�Ȗ��́A�n��S�̂Ƃ��Ă̘A�g�I�ό��U���A�N�V�������A�قƂ�ǂƂ��Ă��Ȃ����Ƃɂ��邪�A����������Q���j�s�s���j�Ƃ��āA�e��A�N�V�����i�����v�����[�V�����Z���^�[�\�z�A�����ό��U���헪�A������M�A�����ό��l�ވ琬�V�X�e���Ȃǁj�ւƒ��肷�邱�Ƃł��낤�ƍl����B
�T�D�Q�l����
���s�s�i2001�|2003�j�u���s�s�ό������N��v���s�s�Y�Ɗό���
���s�s�i2001�j�u���s�s�ό����i�v��\�������₷�v����21�\�v���s�s�Y�Ɗό���
��C�s�i2004�j�u��C�������v�v(��C�s�������ƊǗ��ψ����)
�R��O�i2000�j�u���s�ό��w�v�@��������
�R��O�Ғ��i2001�j�u�������₷�̊ό��헪�v�@��������
��؏��i2000�j�w���ۃc�[���Y���U���_�i�A�W�A�����m�̖����j�x�Ŗ��o������
�i���j
�V���j���[�X�L���������V����
|
 |
�w���v |
|
|
���̃y�[�W�͕ύX����Ă���\��������܂��B���݂̃y�[�W���e������������m�F�ł��܂��B
��HTML�o�[�W�����Ƃ��ĕ\������ہA���C�A�E�g�����ꂽ��A�������ǂ߂Ȃ��Ȃ�ꍇ������܂��B���������������B
|
|
Yahoo! JAPAN�̓y�[�W���̃R���e���c�Ƃ̊֘A�͂���܂���B |
�@ |
�@ |
|
 |
�@ |
�����j���[�X�F 3��20���i���j15��12���X�V
�g�b�v|�g�s�b�N�X|����|�C�O|�o��|�|�\|�X�|�[�c|�R���s���[�^|�n��|�ʐ^|����|�t�H�[����
�Љ�-����-�l-���C�u�h�A�E�j���[�X-���C�u�h�A�EPJ�j���[�X
|
�@ |
[PR]
�y�������Ɏ��������I�z�T�C�{�E�Y�ȒP�O���[�v�E�G�A�̊��p�p
[PR]
���������H�_���f�B�n�E�X�V�C���[�W�L�����N�^�[CM�I���G�A���I
[PR���]
�y���ځz���̏t�b��� �g�l�C�̓s�S�̃}���V�����h�������낢�B
�Љ�
�t�H�[�����F�k���A�W�A�ł̌𗬓W�]�A�T�O�l�Q���|�|���s�E������@�^���s
�@�o�ς���A�l�ޖʂŖk���A�W�A�ł̌𗬁E�A�g��W�]����u�k���A�W�A�E�A�J�f�~�b�N�E�t�H�[�����Q�O�O�T�������s�v���P�X���A������̋��s���T�[�`�p�[�N�ŊJ���ꂽ�B�{�������Ɏ����ǂ�u����Q�S�O�̌l�E�c�̂ł���u���{�C�A�J�f�~�b�N�E�t�H�[�����v�̎�ÂŁA�P�O��ځB����̌����҂��ƊW�ҁA��ʂ̎s�����T�O�l���Q�������B
�@�_�C�L���H�ƂŒ����S���o�������锪�ؒ匛�E���Y�Ƒ��w�@�u�t�́A��C�ł̓��Ѝ��ي�Ƃ̍��������Ɩ��p�G�A�R�����Y�̔��̎��т��Љ�B���i�J����̔��Ȃǂ��܂߂����ƑS�̂ō����Ɠ����x���̋Z�p�ړ]��i�߂邱�Ƃ��A���n�ł̍����Y���̎����ɂȂ���A���荑�̌o�ϐ����𑣐i����Ƃ����B�܂��A�������������Ԃ̌o�ό𗬂̖W���Ƃ��āA����Y�̖����_�ЎQ�q�ƒ����̈�����`������������B
�@�i�s�a�Ŗk�����������Ȃǂ��C������؏��E��㖾��勳���́A�Ƃ��ɗ��j�s�s�ł��鋞�s�Ɩk���̊O���l�ό��q�K��ɂ��Ĕ�r���́B���s�̓A�W�A��������̏W�q���x��Ă��邱�Ƃ������A��[�Z�p��t�@�b�V�����ȂǗ��j�����ʈȊO�ł����͂�����Ă����K�v���w�E���A�k���Ƃ̘A�g�������B
�@�؍��Ɠ��{�̒n�惌�x���ł̌𗬂�i�߂邽�ߍ�N�P�Q���ɔ��������u�C���l�b�g���[�N�v��\�̏������E�����ّ吭��Ȋw���������́A���R�Ɩk��B�A���߂Ȃǂł̌𗬎��т��Љ�B�u���ƊԂ̊W�Ƃ͕ʂɁA�l�X����炷�n��Ԃő��l�ȃl�b�g���[�N���`�����邱�Ƃ��d�v�v�Ƒi�����B
�@���ʂł́A�V��P�F�E���Ð��쏊�����S���i���ے����A�p�����r�o�⎑������̍팸�ȂǓ��Ђ̊��ւ̎��g�݂�B���O���琷��Ȏ��^���������B�y���c�T�V�z
�@
|
2005�N03��20��14��22�� |
�Љ�ꗗ |
|
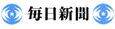 |
Copyright 2003-2005 THE MAINICHI NEWSPAPERS. All rights
reserved. |
�@ |
|
|